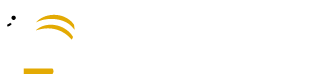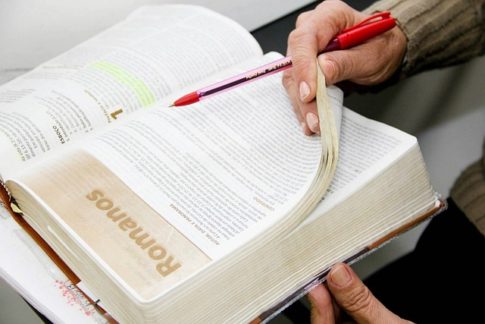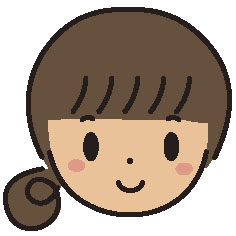
劣等感を感じることってありませんか?
私は高校生くらいの頃が劣等感のピークだったように思います。
大人になってからも、
自分が望んでいても手に入らないものがあるときに苦しい気持ちになっていました。

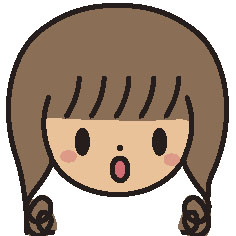
どう付き合っていけばいいの?
この記事では、
- 劣等感とはどういうもの?
- 劣等感との付き合い方
環境の中で劣等感を感じてしまう

劣等感とは、「自分が他人よりも劣っている」という感情をいいます。
容姿や性格、人間関係、学歴など、何に劣等感を持つかはさまざまです。
まわりが「持っている」人ばかりの環境の時ってけっこうしんどいですよね。
- まわりはみんな結婚してる
- まわりはみんな美大出身だ
- まわりはみんな子持ちだ…etc.
まわりがみんな似た状況の時は話題が偏りがちになり、
自分だけ取り残されている気分になってしまいます。

でも考えてみたら、それはただの環境です。
そこにいるから劣等感を感じてしまうだけで、違う環境にいるときは劣等感を感じなくなります。
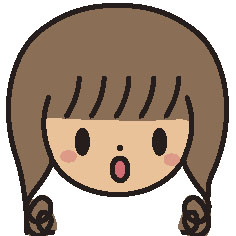
つまり、自分本来のものは変わらないってこと。
劣等感を感じたらその環境を離れてもいいんです。
劣等感は「ある」もの
劣等感は、胸がチクリとする感じ。
そして「ある」ものです。
劣等感を持っている自分は嫌だとか、
劣等感をなくしたい、捨てたいと思うかもしれません。
ですが、劣等感は「ある」もの。
なくそう、捨てようとすることでより意識してしまうことになります。
心理学者のアドラーは、劣等コンプレックスと優越コンプレックス、
そしてそれとは別のものとして劣等感があると言っています。
簡単に言うと…
劣等コンプレックス…「自分には~がないからできない」と思うことで自分の課題と向き合わない。
優越コンプレックス…「自分にはこれがあるからあの人よりも上だ」と思うことで自分の課題と向き合わない。
劣等感…胸がチクリとする感じ。ただ「ある」もの。
劣等感を「なくそう、捨てよう」とする努力は、
優越コンプレックスを育てることになりかねません。
劣等感はまず「ある」ものだと受け入れることで、感情を歪めずに次に進むことができます。
- 劣等感は「ある」ものだと受け入れる
- 自分の中の焦点を当てる位置を変える
というステップが有効だと思います。
劣等感を感じたらcanに焦点を当てる
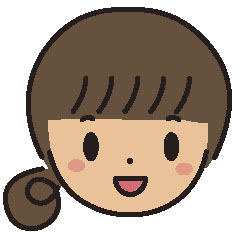
簡単に言うと
- must=ねばならない
- will=したい
- can=できる
この3つの態度は、自分の中にどれも「ある」ものです。
大切なのは、そのどれに焦点を当てるかということ。
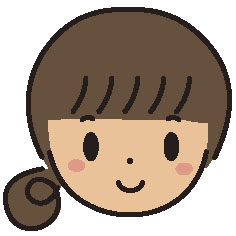
mustは「~しなきゃならない」という義務感
やりたくないことを嫌々やっているという態度です。
やることがmustばかりだと苦しくなってしまうでしょう。
willは「~したい」「~が欲しい」「~ならいいのに」という態度
自分の好きなこと向かいたいことを意識する言葉で、悪いものではありません。
ただ、willばかりにとらわれていると「ないものねだり=劣等感」になりかねません。
劣等コンプレックス、優越コンプレックスもwillに心の焦点を当てている状態と言えます。
canは「~できる」
この「できる」は与えられた能力、才能というニュアンスです。
生まれつきのものだけでなく、努力して手に入れたもの、身に付けたものも含みます。
自分が持っているもの、今できること、与えられてできること
それをまわりに貢献できることが、この「できる」という態度になります。
劣等感を感じたら、canに焦点を当てるのがポイントです。
「これができるもんね!(だからあの人より上だ)」という優越コンプレックスにするのではなく、
天から与えられた「自分にできること」でまわりに貢献していくことを意識しましょう。
まとめ
劣等感は胸がチクリとする感じで、あまり感じたくないものですよね。
ですが、劣等感は環境によって左右されるもので、自分本来のものとは違うものです。
- 劣等感は「ある」ものだと受け入れること
- 本来の自分に与えられたもの=can(できる)に焦点を当てること
劣等感はあるもの。
だけど焦点の位置を変えることで、より自分の望む生き方ができるようになると思います。