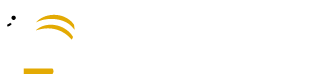Contents
使いづらい押入れを改造
築30数年の中古一戸建てのわが家。
2階の和室を、フローリングにDIY改装中です。
この部屋には、半間の押入れがあります。
上段・下段と、天袋がある一般的な構造です。
押入れって、布団の収納には良いけれど、
奥行きがあって使いづらかったりしますよね。
特に天袋の奥のほうは、踏み台を使っても手が届かない(-_-;)
今回はこの押入れを改造します!
アフター画像はこちら↓
改造のポイントは
- 中板をはずし、天袋の半分を吹き抜けにする
- はしごを設置して、天袋(半分)と屋根裏の収納を出し入れしやすくする
ここまでの工程を紹介しますね♪
※今後、はしごの右側に収納棚を設置して、トビラを作ります。
棚は、ウォークインクロゼットのように、押入れの中に入って利用。
(はしごを使わない時は、壁にピッタリつけて立てられます)
中板を外す
押入れの中板を外します。
中板は、手順を踏めば、キレイに労力少なく外すことができるようです。
三方にある押さえ板を外す
バールなどで、押さえ板を外します。
細い釘が使われていて、簡単に外れます。
中板を外す
中板も、細い釘で止まっています。
下から根太(ねだ)を金槌でコンコン叩くと、
釘が浮いてきます。
↑これが根太。ここを叩きます。
釘が浮いてきたら、釘抜きで抜きます。
根太に沿って、10~15センチくらいの間隔で釘が打ってありました。
外すのがちょっと手間。
ある程度釘を外せば、板を引き剥がせます。
中板が外れました!
根太を外す
根太は、手前と奥の釘を抜けば外れます。
また下から金槌でコンコン打って釘を抜きます。
前框(まえかまち)を外す
手間の太い板が前框(まえかまち)。
両側を釘で止めてあるので、手前から金槌で叩きます。
ガンガン叩く。
けっこうな音がしてますがσ^_^;
このように釘3本でしっかり止めてありました~。
後框(うしろかまち)を外す
奥にあるのが後框(うしろかまち)です。
壁との間にバールを入れてこじります。
こちらもしっかりしてる…。
がんばる。
取れました!
これで押入れが一通り、スッキリ!
床に羽目板を張る
今回は、押入れの床も張り替えることにしました。
踏み台に乗ってたら、床が破れて落っこちたそうなんで(゚o゚;;
押入れの床はわりと薄いです。(劣化もあるんでしょうが^^;)
中板の時と同じように、三方の押さえ板を外します。
.
丸のこも駆使して、バリバリ剥がしちゃいました。
押入れの床下は、こんな感じ。
ここは写真ないですが…^^;
12ミリの合板をビス止めした上に、
10ミリ厚の羽目板を張りました。
羽目板はボンドは付けず、ミニビスのみで止めています。
ワトコオイルのミディアムウォルナットで塗装しました。
床板は計22ミリの厚みです。これなら床が抜ける心配なし^ ^
天袋を半分吹き抜けにする
天袋の板を、半分吹き抜けにしちゃいます。
小さいのこぎりで切りました。
不要な根太は、釘を抜いて外します。
吹き抜け完了!
屋根裏を収納に活用する
板が乗せてあるだけで、開くようになっていました。
(2階のもう一部屋の押入れも、そうなっています。)
我が家の屋根裏は、柱などあって簡単に人が入れる感じではないけれど、
入り口のまわり(手が届く範囲)は収納スペースとして使えます。
はしごを作る
ロフトベッドのはしごの記事でも、工程を紹介しています。
今回はざっくりなので、詳しくはそちらを参考にしてください♪
ステップの幅は320ミリ
ステップの間隔は250ミリ
木材を立てかけて、角度を決めます。
床に平行に印を付けて、カットします。
脚に平行に、踏み板をつける位置に印を付けていきます。
丸のこの歯を10ミリ出るように調整して、溝を切ります。
間にも数本切り込みを入れます。
ノミを使って、間の木材を落とします。
簡単にポロポロ取れますよ♪
軽くヤスリをかけて、溝切り完了!
両側、溝が切れました。
今回の木材は角ばっていて、はしごとして握ると痛い^^;
ホビーカンナで角を落としました。
組み立てる前に、ワトコオイルのダークウォルナットで塗装しました。
上の角材は、無塗装の色です。
塗装するといい感じに♪
ビスで止めていきます。
押入れ内は狭いので、屋外で組み立てました。
できた♪
青空に気持ちいい^ ^
引っ掛けるための切り欠きを作ります。
現場合わせで印を付けて、のこぎりで切ります。
引っ掛けると、こんな感じ。
脚には、すべり止めに5ミリ厚のゴムシートを貼りました。
出来上がり!
ロフトのはしごに比べると、細い木材なので少しグラつきますが、
強度は問題なしです。
ロフトのはしご記事はこちら↓
天袋と天井裏の収納が出し入れしやすくなりました!
ご参考になればうれしいです♪